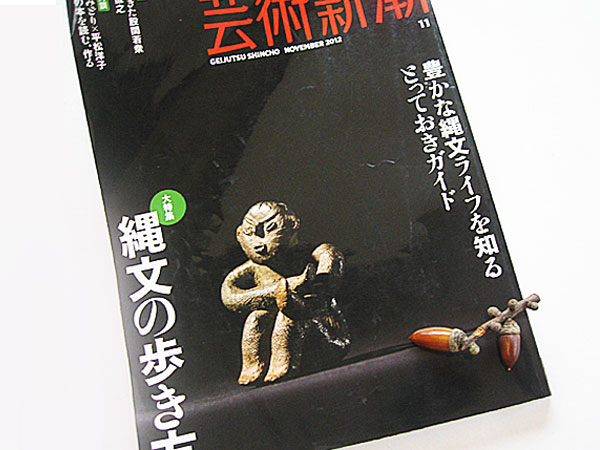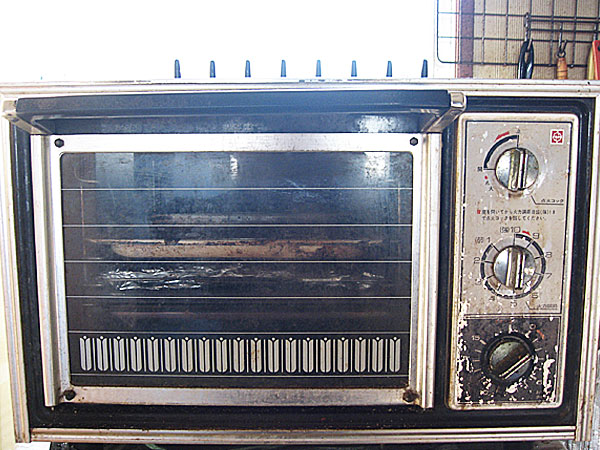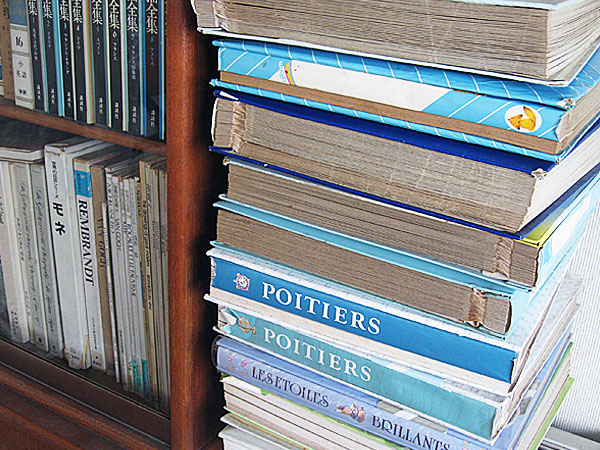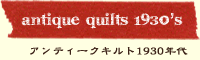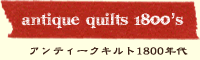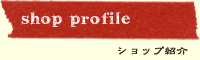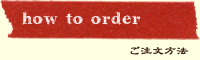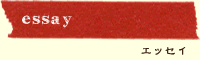リカさんのこと
本名は、Roderica Laymon ロデリカ・レイモン、といいます。
もう、30年以上も前のことです。
私たちは半島の先端の伊良湖岬で小さな民宿を営んでいました。
その頃、1艘のアメリカ籍のヨットが台風の被害を受けて、修理のために
伊良湖港に停泊していました。
そのヨットのオーナーがリカさんでした。
私がカタコトの英語を話せるのを知っていた伊良湖博物館のO氏がリカさんを
私の店に案内してくれたのが、リカさんとの最初の出会いでした。
ご主人が退職されたのを機に、リカさんはご主人とヨットで世界一周の旅をしていました。
以来、長い間の文通が始まります。
インターネットなどなかった時代です。
ある時は手書きで、ある時はタイプライターで書いた手紙をポストに投函します。
アメリカまで届くには、最低でも航空便で1週間かかりました。
リカさんは、とても素敵なおばあちゃんです。
私のいろいろな相談に、いつもとても親身になってアドバイスしてくれました。
前向きで、活動的で、新しいことにもどんどん挑戦しました。
パソコンが普及すると、インターネットも始めました。
ご主人が癌で亡くなってからも、手紙とメールの交換は続きました。
数年前に、リカさんの娘さんから突然のメールが届きました。
リカさんが倒れて、今は施設のお世話になっていること、記憶があいまいで
物事をちゃんと理解できないこと、など。
リカさんのパソコンの中にあった交友のあった人たちのアドレスへの
一斉送信でした。
その後、リカさんとは連絡が取れていません。
何度も、マチコ、遊びにいらっしゃいと声をかけてくれたのに、再会が果たせなかったことが
心残りです。
そして、今でもリカさんがいてくれたら、と思うことがたくさんあります。
会いたい気持ちで、いっぱいです。