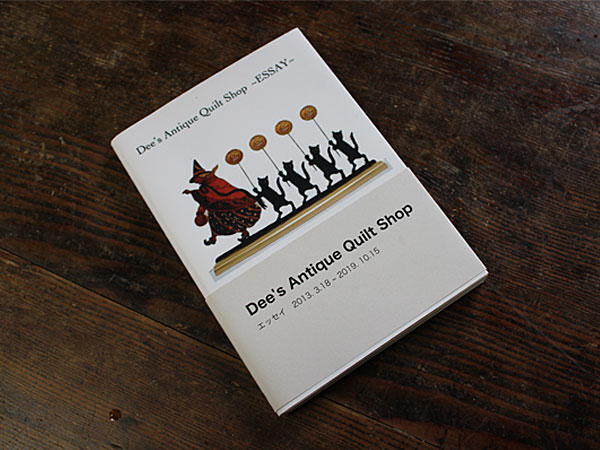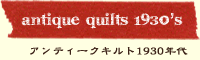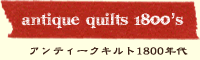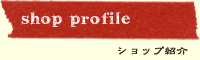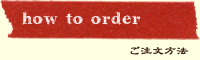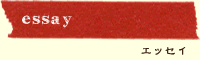イギリスのアンティークドア
家族との間でちょっと気まずいことがあって、プチ家出よろしくひとり京都行きの列車に乗りました。
かねてから行きたかった京都のウエリントンさん、アンティークドアの専門店です。
この家に引っ越す何年も前、セルフビルドまたはハーフビルドで家を建てたいという夢がありました。
いろいろな事情でその計画が頓挫して、今の中古住宅を購入することになったのですが、
その頃はまだ、家のためのいろいろな建具や部材を探している時でした。
京都駅から伏見区のウエリントンまでは、とても遠くて電車やバスを乗り継いでやっと
たどり着いたのを覚えています。
お店に入り、いろいろなドアを見て回るうちに、あるドアの前で足が止まりました。
美しいドアでした。このドアのほか無いと思いました。
そういうことって、アンティークキルトとの出会いでもありますよね。
私が考えていたのは、このドアを玄関ドアに、ということでしたが店員さんに聞いてみると
室内用のドアとのことで、それでもメンテナンス担当の職人さんに玄関用としても使えることを
確認してくれました。
その後、最後の調整を経て家に送られて来たわけですが、購入したこの家で結果室内ドアとして
使うことになりました。
取り付けてみると、最初からここにあったドアのようにしっくりと馴染んでいます。
イギリスからはるばる海を渡ってやってきたこのドア、以前はどんな家でどんな家族の会話を
聞いていたのかと想像するのは、アンティークのキルトが縫われた経緯を想像するのと
似ています。