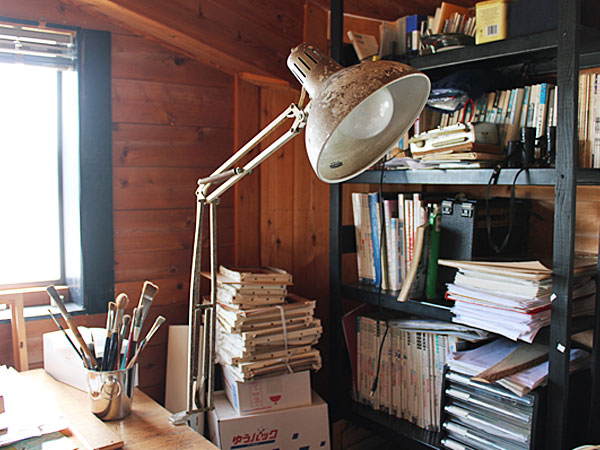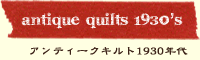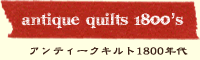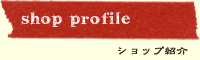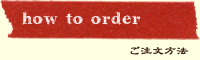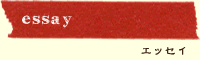半世紀
山肌をジグザグに登って行く「箱根登山鉄道」は別名「あじさい電車」とも
呼ばれています。6月7月になれば、線路の両側に色とりどりのあじさいが
花を咲かせます。
その箱根登山鉄道に乗って、箱根彫刻の森美術館へ行ったのは1975年の7月でした。
彫刻の森は、7万平方メートルの森の中に120点の屋外彫刻が配置された
オープンエアミュージアムです。
私は当時、東京の短大で英語を学ぶ短大生、同郷の夫は同じく東京の予備校に
通う浪人生でした。結婚は、していませんでした。
どういう経緯で、箱根へ行ってみようと思ったのか、よく覚えていません。
ただ、歳を取ると妙に昔のことが懐かしく、ここ数年もういちど彫刻の森へ
行ってみたいという思いが高まっていました。
それも49年前と同じ、あじさいの咲く季節に。
まだよぼよぼではないけれど、同じ年の人が病気になったり亡くなったりするのを
聞くと、「できる時に」という思いはいろいろなシーンで考えます。
それで、思い切っての日帰り旅行。
あの頃と変わったのは、外国人旅行者が増えたことかな。
49年前に撮った写真のデータを持って行って、同じ場所の同じアングルで写真を
撮りました。帰宅後、その写真を見比べて半世紀の歳月の長さを思います。
この写真は49年前のもの。若い子も、いつかおばあちゃんになります。
1930年代のキルトは、誕生から約1世紀ですね。